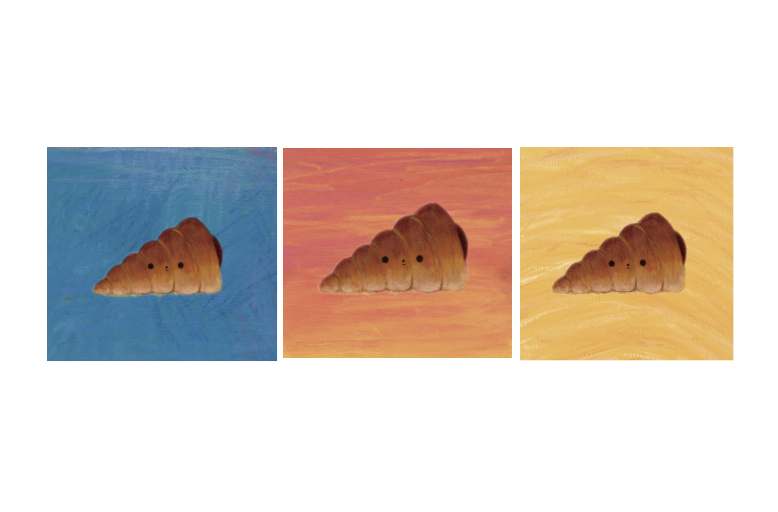
絵本作家の祐彩(ゆうせい)です。
絵本を読む時間って、実は「ふたつの物語」が同時に動いている気がします。
ひとつはページの中で進んでいくおはなし。
もうひとつは、ページの外。つまり、親子のあいだで生まれる小さな会話や表情の物語です。
たとえば、「どっちがコロネのおしりだと思う?」と尋ねたとき、子どもが一生懸命に考えたり、笑ったり、思いもよらない答えを返してくれる。
その一瞬こそが、絵本のもうひとつの冒険のはじまりなのです。
私、祐彩(ゆうせい)の絵本『コロネのおしりはどっち?』を読んだ親子から、
「読みながら子どもと大笑いしました」
「家族みんなでおしり談義になりました」
といった感想をよくいただきます。
実はその笑いの中に、小さな「自分で考える冒険」が隠れていたりするんです。
正解がないからこそ、子どもは自分の考えを言葉にしてみる。
その瞬間に、物語は「親子のもの」になる。
それが、絵本のいちばん面白いところだと思います。
これもよく読者さんから聞くお話ですが、
絵本『コロネのおしりはどっち?』を読み終えたあと、子どもが何気なくパン屋さんでコロネを見て「コロネのおしりは、やっぱりこっち?」とつぶやく。
こんなふうに、絵本の物語が日常の中に入りこんでくる瞬間があります。
絵本のページを閉じたあとも、おはなしが心の中で続いていく。
それが、コロネに限らず絵本がくれる親子の小さな冒険なのだと思います。
子どもと一緒に絵本を読むとき、大人が答えを急がず、「どう思う?」と問いかけてみる。
子どもの返事に「なるほど!」と笑ったり、思いがけない視点にハッとしたり…。
そのやりとりの中で、大人もまた考える力を思い出すのかもしれません。
絵本は、子どもの成長を見守る時間であると同時に、親自身の感性をやわらかくしてくれる時間でもあると思うのです。
「自分で決める力」は、小さな迷いをくり返す中で育っていきます。
そのときに必要なのは、すぐに正しい答えを見つけることではなく、「いっしょに迷える相手」の存在。
絵本は、そんな時間を自然につくってくれる。
親子が同じページをのぞきこみながら、ひとつの世界を共有すること。
その体験そのものが、子どもの「自分で選びたい」という気持ちをやさしく後押ししてくれるのです。
絵本『コロネのおしりはどっち?』は、コロネが「自分で決める」ことを通して、少しずつ自分のカタチを見つけていく(生み出していく)物語です。
でも、それはコロネだけの話ではありません。
読むたびに、親子それぞれの中でちがう「旅の地図」が描かれていくのです。
絵本を読むたびに発見があるのは、その旅がいつも新しいからかもしれませんね。
「絵本の時間」とは、親が教える時間ではなく、いっしょに感じる時間。
その積み重ねが、子どもにとっての「自分で決める力」となり、親にとっても心がほどけるひとときになる。
今日もまた、絵本をひらくたびに、小さな親子の冒険がはじまっているのですね。
